目次
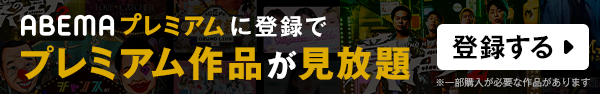
 「かごめかごめ」は怖い歌?その噂の真相に迫る
「かごめかごめ」は怖い歌?その噂の真相に迫る
「かごめかごめ 籠の中の鳥は…」このフレーズを耳にしただけで、どこか懐かしく、同時に少し不気味な気持ちになる方は少なくないのではないでしょうか。「かごめかごめ」は、単なる子供の遊び歌として片付けるにはあまりにも多くの謎と、背筋が凍るような噂に包まれています。この記事では、「かごめかごめ」がなぜこれほどまでに私たちの心を捉え、時に恐怖の対象として語られるのか、その意味と背景を徹底的に解き明かしていきます。数々の都市伝説から、歴史的な資料に基づいた真実まで、この歌に隠された全ての物語を一緒に探っていきましょう。
なぜ「歌ってはいけない」とまで言われるのか?3つの理由
「かごめかごめ」には、「呪いの歌だから歌ってはいけない」という、穏やかではない噂が存在します。多くの人が知るわらべうたが、なぜこれほど強い禁忌のイメージをまとってしまったのでしょうか。その背景には、単一の理由ではなく、少なくとも3つの要因が複雑に絡み合っています。
第一に、歌詞そのものが持つ多義性と不気味さが挙げられます。「夜明けの晩」という、論理的にはあり得ない矛盾した言葉。「後ろの正面だあれ」という、答えようのない謎めいた問いかけ。これらの表現は、聞き手の安定した日常感覚を揺さぶり、言いようのない不安をかき立てます。明確な意味が提示されないからこそ、人々はその「意味の空白」を自らの想像力で埋めようとします。そして、多くの場合、その空白は最も刺激的で記憶に残りやすい「恐ろしい物語」によって満たされていくのです。
第二の理由は、この歌を題材とした数多くの都市伝説の流布です。後ほど詳しく解説しますが、「牢獄で処刑される囚人の歌」「遊郭から出られない遊女の悲劇」「流産した妊婦の怨念」といった、悲劇的な背景を持つ物語が広く知れ渡っています。これらの物語は、歌の曖昧なフレーズに具体的な恐怖のイメージを与え、「かごめかごめ」=「怖いもの」という印象を社会に決定的に定着させました。
そして第三に、過去に流れた「放送禁止」という噂の影響も無視できません。かつて、特に大阪府を中心として「かごめかごめは呪いの歌なので放送できない」という根拠のない噂が広まりました。この話は後に完全な俗説であったことが判明していますが、「公の電波に乗せることすら憚られるほど不吉な歌」という一度植え付けられたイメージは、人々の心に深く、そして長く残り続けているのです。作者が誰なのかも分からず、公式な解説も存在しない。この歌が持つ根源的なミステリーこそが、様々な恐怖の憶測を生み出す最大の土壌となっていると言えるでしょう。
都市伝説はいつから?謎が謎を呼ぶ背景を解説
では、徳川埋蔵金説や明智光秀生存説といった、壮大なスケールの都市伝説は一体いつ頃から語られるようになったのでしょうか。その起源を正確に特定することは非常に困難ですが、これらの説が全国的に広まった背景には、テレビというメディアの存在が大きく関わっています。特に、徳川埋蔵金の発掘を試みるようなテレビの特集番組は、繰り返し放送され、多くの人々の冒険心と好奇心を刺激しました。
これらの都市伝説が人々を強く引きつけるのには、理由があります。それは、歴史上の誰もが知る「未解決の謎」(埋蔵金は本当に存在するのか?光秀は本能寺の変の後どうなったのか?)と、誰もが知る「わらべうた」を結びつけるという、非常に巧みな物語構造を持っている点です。私たちのよく知る「既知」の世界と、ロマンあふれる「未知」の世界が、この歌を介して繋がる。この構造こそが、人々を魅了してやまないのです。
さらに、インターネットの普及が、これらの説の拡散と再生産を加速させました。今や、数えきれないほどのウェブサイトや動画で、様々な角度からの解釈や新たな説が展開されています。しかし、この現象を単なる噂話として片付けるのは早計かもしれません。人々は本気で埋蔵金が見つかると信じているというよりは、歴史の断片的な情報をパズルのように組み合わせ、壮大な「if(もしも)」の物語を構築するプロセスそのものを楽しんでいるのではないでしょうか。その意味で、「かごめかごめ」の都市伝説は、歴史の裏側にあるロマンを味わうための、非常に高度な知的エンターテインメントとして機能しているのです。この歌は、その曖昧さゆえに、どんな歴史ミステリーとも結びつくことができる、最高の「プラットフォーム」として、日本人の集合的な想像力を刺激し続けています。
歌詞に隠された「かごめかごめ」の本当の意味とは?
「かごめかごめ」の本当の意味を探る旅は、歌詞のフレーズを一つひとつ丁寧に読み解くことから始まります。子供の遊び歌としての素朴な顔から、都市伝説の中で語られる恐ろしい顔まで、それぞれの言葉が持つ多重的な意味の世界を覗いてみましょう。
「かごめかごめ」- 囲め、屈め、籠目?言葉の多重解釈
歌の冒頭を飾る「かごめ」という言葉。この一言だけで、驚くほど多様な解釈が存在します。
- 遊びの掛け声説: 最もシンプルで分かりやすいのが、遊びの状況をそのまま表しているという説です。中央にいる鬼役の子供に対して、周りの子供たちが「鬼を囲め、囲め」と呼びかけたり、「鬼は屈め(かがめ)、屈め」と指示したりする言葉が、時を経て訛ったものだと考えられています。
- 籠の編み目説: 竹で編んだ籠の網目模様、すなわち「籠目(かごめ)」を指しているという説です。この籠の目は、正三角形と逆三角形を組み合わせた六角形の形をしており、古くから魔除けの印として使われてきました。この解釈は、後に紹介する徳川埋蔵金説において、呪術的な結界としての「六芒星」へと繋がっていきます。
- 妊婦説: 漢字で「籠女」と書き、籠を抱えているかのように見える女性、つまりお腹の大きな妊婦の姿を指すという説です。この解釈を採用すると、歌全体が妊婦にまつわる悲劇的な物語として読み解かれることになります。
- 処刑場の竹垣説: 処刑場をぐるりと囲む竹垣を「籠目」に見立てている、という不吉な説も存在します。この解釈は、歌全体を囚人の処刑シーンとして捉える「囚人説」の入り口となります。
「籠の中の鳥は」- 囚人、遊女、それとも…?
次に続く「籠の中の鳥は」というフレーズ。これは、物理的、あるいは精神的に自由を奪われた存在の象徴として、様々な悲劇的な人物像に重ねられてきました。
- 遊びのルール上の意味: 本来は、遊びの中で子供たちの輪の中心に座り、目隠しをされた「鬼」役の子供そのものを指しています。周りを囲まれ、目が見えない状態が「籠の中の鳥」に例えられているのです。
- 囚人説: この説では、「籠」は牢獄を、「鳥」はその中にいる囚人を指します。続く「いついつ出やる(いつ出てくるのか)」という歌詞は、いつになったら出所できるのか、あるいは、いつになったら処刑されてしまうのか、という絶望的な問いかけとして響きます。
- 遊女説: 「籠」を遊郭に見立て、そこから出ることが許されない遊女の境遇を歌っているとする説です。華やかな世界の裏で自由を奪われた女性たちの悲しみが込められていると解釈されます。
- 妊婦説: 母親の胎内(籠)にいる赤子(鳥)を指すという解釈です。この場合、一見穏やかな表現に見えますが、この後の歌詞で待ち受ける悲劇を暗示する、非常に不吉な前振りとして機能します。
「夜明けの晩に」- 矛盾した言葉が示す不気味な情景
「夜明けの晩に」というフレーズは、この歌が持つ不気味さの核心部分と言えるでしょう。夜明けであり、かつ晩である時間など、現実には存在しません。この論理的な破綻は、この歌が描いているのが日常的な出来事ではなく、何か特別な、あるいはこの世ならざる異常な状況であることを強く示唆します。
都市伝説の中では、この矛盾した言葉に様々な意味が与えられます。例えば、囚人説では「夜明け=処刑が執行される時間」と「晩=人生の終わり」を重ね合わせた、死の瞬間そのものを表す言葉だとされます。あるいは、「もう二度と本当の朝を迎えることがない」という、永遠の絶望を表現しているとも解釈されます。
一方で、徳川埋蔵金説では、このフレーズは具体的な時間を指す暗号として読み解かれます。「夜明けの晩」とは、太陽が昇る直前の、まだ空が薄暗い特定の瞬間を指しており、その時にだけ宝のありかを示す決定的な「影」が現れる、と考えられているのです。
「鶴と亀が滑った」- 縁起の良いシンボルの崩壊が意味するもの
長寿と吉兆の象徴として、日本では古くから尊ばれてきた鶴と亀。その縁起の良い二つの生き物が「滑った」という表現は、聞き手に強烈な違和感を与え、何らかの決定的な凶事や秩序の崩壊を予感させます。
- 縁起の悪い出来事: 最も直接的な解釈は、縁起の良いものの象徴が失われた、つまり「死」「破滅」「計画の失敗」といった、取り返しのつかない不吉な出来事が起こったことを示している、というものです。
- 囚人説・遊女説: 囚人説では、脱獄を試みたものの失敗し捕らえられたり、ついに死刑が執行されたりする様を表すとされます。遊女説では、美しかった遊女が年老いて客からの人気を失い、その座から滑り落ちる悲哀を描いていると解釈されます。
- 妊婦説: この説においては、歌詞が最も悲劇的な意味を帯びます。妊婦が何者かによって突き飛ばされて転倒し、お腹の子を流産してしまった決定的な瞬間を描写している、とされているのです。
- 徳川埋蔵金説: この説では、言葉の読み替えという大胆な解釈が行われます。「滑った」を「統べった(すべった)」、つまり「統治した」「支配した」と読み替えるのです。これにより、歌詞は「鶴と亀の像が天下を統治する場所」、すなわち徳川家の権威の象徴である墓所のありかを示している、という暗号に変わります。
「後ろの正面だあれ」- 遊びのルールを超えた恐怖の問いかけ
歌の最後を締めくくるこのフレーズは、遊びのクライマックスであると同時に、都市伝説においては死や裏切りに直面した人物の最後の言葉として、最も恐ろしい意味を帯びる部分です。
- 遊びのルール上の意味: これは、目隠しをした鬼が、歌が終わった瞬間に自分の真後ろに立った子供は誰なのかを当てる、という遊びのルールそのものを表す、純粋な言葉です 1。
- 囚人説: 都市伝説の中で最も有名な解釈がこれです。首を斬り落とされた囚人が、最後に見た光景、つまり自分の体を斬った処刑人は誰なのか、あるいは、地面に転がった自分の首から、自分の亡骸を見下ろしているのは誰なのか、と問いかけているという、非常に残酷な場面描写です。
- 妊婦説: 転倒させられ、お腹の子を失った妊婦が、朦朧とする意識の中で「私を突き飛ばしたのは一体誰なの?」と、犯人に対して問いかけている怨念の言葉とされます。
- 権力者説: より抽象的な解釈として、世の中の出来事を表向きではなく、裏で糸を引いて操っている黒幕(=後ろにいるのに、正面にいるかのように影響力を持つ存在)は一体誰なのか、という社会の権力構造そのものへの問いかけだとする説も存在します。
このように、一つの歌詞がいかに多様な物語の「器」になりうるか、以下の表で比較してみましょう。各説が、歌詞の断片を自らの物語に合わせて巧みに解釈し、一つの世界観を構築している様子が一目で分かります。
| 歌詞のフレーズ | 遊び歌としての意味 | 囚人説 | 遊女説 | 妊婦説 | 徳川埋蔵金説 | 明智光秀説 |
| かごめかごめ | 鬼を囲む掛け声 | 処刑場の竹垣 | 遊郭の格子 | 籠を抱くような女性 | 徳川家ゆかりの地の結界 | – |
| 籠の中の鳥 | 鬼役の子供 | 牢獄の囚人 | 郭に囚われた遊女 | 胎内の子 | 日光東照宮の鳥居 | 徳川に仕える光秀 |
| 鶴と亀が滑った | 歌のリズム | 脱獄の失敗/死刑執行 | 老いによる人気の陰り | 転倒による流産 | 鶴と亀の像が統治する場所 | 敦賀と亀岡の統治 |
| 後ろの正面だあれ | 後ろの子を当てる | 処刑人は誰か | 次の客は誰か | 転倒させたのは誰か | 宝塔の後ろの祠 | 自身の正体は誰か |
この表は、都市伝説がどのように「作られる」かを示唆しています。例えば、「籠の中の鳥」というフレーズは、どの説においても「自由を奪われた存在」という共通のイメージで解釈されています。聞き手は、単に説を鵜呑みにするのではなく、「なるほど、この言葉をこのように解釈して、あの壮大な話に繋げているのか」と、その構造自体を分析的に楽しむことができるのです。
最も有名な都市伝説:徳川埋蔵金のありかを示す暗号説
数ある「かごめかごめ」の都市伝説の中でも、群を抜いて壮大で、具体的な物的証拠とされるものが提示されているのが「徳川埋蔵金説」です。この説は、わらべうたが日本史上最大級の謎の一つ、徳川幕府が隠したとされる莫大な財宝のありかを示す、精巧な暗号地図であると主張します。まるで宝探しに参加しているかのような臨場感をもって、その驚くべき内容を検証していきましょう。
地図上に浮かび上がる六芒星と「籠の中の鳥居」
この説の壮大さは、まずそのスケールにあります。徳川家康が江戸の鎮護と繁栄を願い、関東地方に建立した主要な寺社仏閣を地図上で線で結ぶと、そこには驚くべきことに、籠の網目模様、すなわち「六芒星(ヘキサグラム)」が浮かび上がるというのです。
この説によれば、歌の冒頭の「かごめ」とは、この六芒星によって作られた、徳川の財宝を守るための巨大な呪術的結界そのものを指しているとされます。そして、続く「籠の中の鳥は」という歌詞は、さらに核心に迫ります。この「鳥」とは「鳥居」が訛ったものであり、六芒星の結界の中心に位置する聖地、すなわち日光東照宮の大鳥居を指し示している、と解釈されるのです。
この解読によって、歌の舞台は漠然とした場所から、具体的な「日光東照宮」へと一気に絞り込まれます。聞き手は、壮大な謎解きの第一の扉が開かれたかのような興奮を覚えることでしょう。
鶴と亀の像が示す家康の墓所:鍵は朝日の影にあり
暗号解読の旅は、日光東照宮の最も神聖な場所、奥宮へと進みます。歌のクライマックスである「鶴と亀が滑った」というフレーズこそ、徳川家康が眠る墓所に隠された、埋蔵金の場所を示す決定的なヒントであると、この説は主張します。
実際に、家康の墓所である宝塔の前には、鶴と亀の見事な彫像が安置されています 6。この説の支持者たちは、「滑った」を「統べった(天下を統治した)」と読み替えます。そして、「夜明けの晩に」、つまり朝日が昇る特定の瞬間に、この鶴と亀の像に光が当たり、その影が指し示す方向こそが、埋蔵金が眠る場所なのだと解読するのです。
さらに、「後ろの正面だあれ」という最後の問いかけは、家康の墓所である宝塔の真後ろにひっそりと佇む小さな祠(ほこら)を指しているとされます。歌の全てのピースが、日光東照宮の奥宮という一点で見事に繋がるかのように思えます。この説をさらに補強するのが、東照宮の彫刻に見られる不可解なディテールです。例えば、奥宮の鶴の彫像の足には、まるで飛び立つのを妨げるかのように金輪がはめられています。これは、埋蔵金のありかを示す影の位置が、鶴が動くことで変わってしまわないように固定するためではないか、といった憶測を呼び、謎を一層深めているのです。
この説の信憑性は?方位が示す決定的な矛盾点
地図上の六芒星、鳥居、鶴と亀の像、そして家康の墓所。まるでミステリー小説のように伏線が回収されていく、この精巧にできた徳川埋蔵金説。しかし、その根幹を揺るがす、科学的かつ決定的な矛盾点が存在します。
この説の核心は、何度も述べたように「朝日が鶴と亀の像を照らし、その影が宝塔(=埋蔵金の場所)を指し示す」という点にあります。これは、検証可能な物理現象です。しかし、実際に日光東照宮の奥宮における宝塔と鶴亀の像の位置関係、そして太陽が昇る方角を精密に調査すると、悲しいかな、朝日が差したとしても、その影は宝塔とは全く異なる方向を向いてしまうことが物理的に証明されています。
この事実は、何を意味するのでしょうか。それは、この徳川埋蔵金説が、歴史的な事実を暗号化したものではなく、むしろ「史実の断片を巧みに組み合わせて創作された、見事なフィクション」である可能性を強く示唆しています。この説の最大の魅力は、その「物語としての完成度の高さ」にあります。しかし、最後の最後で「物理法則」という動かしがたい現実に阻まれてしまうのです。この説を単に「間違い」として切り捨てるのではなく、「近代に生まれた最も成功した神話の一つ」として捉えることで、人々が歴史に何を求め、どのような物語に心を動かされるのか、という文化的な深層が見えてくるのかもしれません。
もう一つの巨大な謎:明智光秀は生きていた?南光坊天海=同一人物説
徳川埋蔵金説と双璧をなす、もう一つの壮大な歴史ミステリー。それが、「本能寺の変」で主君・織田信長を討った明智光秀が、実は死なずに生き延び、徳川家康の側近・南光坊天海として江戸幕府の礎を築いた、という「明智光秀=南光坊天海 同一人物説」です。この説は、「かごめかごめ」を、歴史上の重要人物の数奇な運命を暗示する、極めて個人的なメッセージとして読み解いていきます。
天海が残した数々の痕跡と「かごめかごめ」の繋がり
歴史の公式記録によれば、明智光秀は1582年の山崎の戦いで命を落としたとされています。しかし、その遺体は発見されておらず、これが後世に様々な憶測を生む原因となりました。一方で、南光坊天海という僧侶は、徳川家康に深く信頼され、江戸の都市計画から日光東照宮の建立まで、国家的な大事業を次々と主導した実在の人物です。しかし、驚くべきことに、彼の前半生は全くの謎に包まれており、出自や経歴を示す確かな記録はほとんど存在しません。
この歴史の「空白」を埋める形で浮上したのが、この同一人物説です。天海が成し遂げた偉業は、光秀ほどの卓越した知謀と幅広い教養を持つ人物でなければ不可能だったのではないか、という推測がその根底にあります。この噂は後世の創作というだけではなく、江戸時代の幕府内部でさえも密かに囁かれていたとされます。そして、この説を強力に裏付けるとされる物証が、日光に存在します。日光には、天海自身が「明智の名を残したい」と語って名付けたとされる「明智平」という地名が、今もなお実在しているのです。
「鶴と亀」が示す地名:敦賀と亀岡の謎
この説において、「かごめかごめ」の歌詞は、天海が自らの正体を暗示するために残した暗号として解釈されます。特に重要なのが「鶴と亀が滑った」というフレーズです。徳川埋蔵金説では、これを日光東照宮の像と解釈しましたが、光秀説では全く異なる意味を見出します。
ここでいう「鶴」と「亀」は動物ではなく、明智光秀が生前に統治していた地名を指すというのです。「鶴」は、現在の福井県にある「敦賀(つるが)」。「亀」は、現在の京都府にある「亀岡(かめおか)」です。
そして、「滑った」は、ここでも「統べった(統治した)」と読み替えられます。つまり、この一節は、「かつて私(光秀)は、敦賀と亀岡という地を統治していた者である」という、天海から後世への、あるいは秘密を共有する仲間への、極めて個人的なメッセージであると読み解かれるのです。
「後ろの正面」はどこ?光秀の故郷から見える岸和田の本徳寺
この説の最もミステリアスで、多くの人々を惹きつけてやまない点が、「後ろの正面だあれ」という最後のフレーズを、日本の地理に当てはめて解読する、驚くべき発見です。
まず、明智光秀の出身地の一つとされる岐阜県可児市に立ちます。そして、天海がその生涯をかけて造営した日光東照宮の方角を向きます。その状態で、「後ろの正面」、つまり体の真後ろを振り返ると、その方角の先には、一体何が存在するのでしょうか。
驚くべきことに、その方角の先には、大阪府岸和田市に位置する「本徳寺」というお寺が、ほぼ一直線上に存在します。そして、この本徳寺には、日本で唯一現存すると言われる、極めて貴重な明智光秀の肖像画が大切に所蔵されているのです。この奇跡的としか言いようのない地理上の一致が、単なる憶測に過ぎなかったこの説に、強い説得力と抗いがたいロマンを与えています。
春日局との関係は?歴史の裏側で動いた人物たち
この壮大なミステリーをさらに補強するのが、3代将軍・徳川家光の乳母として絶大な権力を誇った、春日局の存在です。彼女は、実は明智光秀の重臣であった斎藤利三の娘であり、天海との間に、歴史の裏側をうかがわせる意味深な繋がりがあったとされています。
これは俗説の域を出ませんが、春日局が江戸城で初めて天海と対面した際、周囲の人間には意味の分からない「お久しぶりでございます」という挨拶を交わした、という逸話が残っています。もしこれが事実であれば、彼女は天海の正体が、かつての父の主君であった明智光秀その人であると、最初から知っていたことになります。
このことから、「かごめかごめ」は、光秀の生存という徳川幕府の根幹を揺るがしかねない最高機密を知る者たちの間でだけ通じる、秘密の合言葉だったのではないか、という想像まで掻き立てられます。この説の魅力は、歴史の公式記録では「逆賊」として断罪された光秀が、実は江戸の平和の礎を築いた最大の功労者だった、という「敗者」を「勝者」に書き換える物語の力にあります。公式の歴史だけでは満たされない、もう一つの物語への渇望が、この説を今なお生き永らえさせているのです。
専門家が解説する「かごめかごめ」の歴史的な真実
ここまで、背筋の凍るような怖い噂から、徳川埋蔵金や明智光秀といった壮大なスケールの都市伝説まで、「かごめかごめ」にまつわる様々な物語を探ってきました。しかし、これらの説は果たして歴史的な事実に耐えうるものなのでしょうか。最後に、文献資料などの客観的な証拠に基づき、専門家が解き明かす「かごめかごめ」の本当の姿に迫ります。多くの人が知らない、この歌の本来の歌詞と遊び方を知れば、きっとこれまでのイメージが覆されることでしょう。
最古の記録は1820年『童謡集』:現在の歌詞とは全く違った
「かごめかごめ」の歌詞の起源を遡る上で、現存する最も古い記録は、江戸時代後期の1820年(文政3年)ごろに、釈行智という人物によって編纂された『童謡集』という書物です。この書物には、確かに「かごめかごめ」という題のわらべうたが収録されています。
しかし、そこに記されていた歌詞は、私たちの知るものとは似ても似つかないものでした。その歌詞は、「かごめかごめ 籠の中の鳥は…」ではなく、「つるつる つっぺぇつた」や「なべのなべのそこぬけ」といった、現代の私たちには意味を解読することが困難な言葉の羅列だったのです。
ここで最も重要な事実は、この現存最古の記録には、これまで見てきた数々の都市伝説の根幹をなす**「鶴と亀が滑った」や「後ろの正面だあれ」といった決定的なフレーズが、一切登場しない**ということです。この事実は、都市伝説の信憑性を考える上で、極めて重大な意味を持ちます。
本来の遊び方は「後ろの正面」ではなかった?「くぐり型」の遊びとは
驚くべきことに、異なっていたのは歌詞だけではありませんでした。遊び方そのものも、現在私たちが知っているものとは大きく異なっていたことが分かっています。
現代の「かごめかごめ」は、鬼が自分の真後ろにいる子を当てる、いわゆる「後ろの正面型」の遊びです。しかし、江戸時代の記録に見られる「かごめかごめ」は、「くぐり型」と呼ばれる、よりダイナミックな集団遊びが主流でした。これは、子供たちが輪になって手をつなぎ、その腕でアーチを作ります。そして、列になった他の子供たちが、歌に合わせてそのアーチの下を次々とくぐり抜けていく、というものです。歌の最後にアーチの下にいた子が捕まり、次の鬼になる、というルールでした。1830年代に編纂された『幼稚遊昔雛形』という文献にも、わらべうたとしてのかごめかごめの記録が確認されており、そこからも当時の子供たちの活発な遊びの様子がうかがえます。
いつから今の形に?メディアの普及が全国に広めた特定のバージョン
では、私たちが現在当たり前のように知っている「かごめかごめ」は、いつ、どのようにして生まれたのでしょうか。
もともと「わらべうた」というものは、口伝えで広まっていく過程で、地域ごとに少しずつ歌詞やメロディが変化していく性質を持っています。「かごめかごめ」も例外ではなく、かつては日本各地に様々なバリエーションが存在していました。
私たちが現在知るバージョンは、昭和初期に音楽家であった山中直治氏が、千葉県野田市に伝わっていたものを採譜し、記録したものです 3。そして、この「野田市バージョン」が、レコードやラジオ、そして戦後の学校教育における音楽の教科書といった、近代的なメディアを通じて全国へと一気に広まり、事実上の「標準形」として定着したのです。つまり、私たちが「本来の歌詞」だと信じているものは、実は数多く存在した地域的なバージョンの一つが、メディアの力によって突出して有名になったもの、と言うことができます。
結論:本来は子供たちの健全な遊び歌だった
これまでの歴史的な事実を整理すると、一つの明確な結論が導き出されます。「かごめかごめ」は、本来、呪いや怨念、あるいは歴史の暗号といった恐ろしい意味を全く持たない、純粋な子供たちのための健全な「わらべうた」であった、ということです。江戸時代の記録が示すのは、子供たちが日々の遊びの中で自然に生み出し、歌い継いできた、生き生きとした文化としての姿です。
この事実は、これまで見てきた都市伝説に決定的な一撃を与えます。徳川埋蔵金説も明智光秀説も、その論理の前提は「『鶴と亀』や『後ろの正面』という歌詞が、江戸時代初期から存在した」という点にあります。しかし、歴史的な資料は、その大前提を明確に否定しています。つまり、暗号とされる歌詞は、その暗号が作られたとされる徳川家康や明智光秀の時代には、まだ存在していなかったのです。このことから、私たちが知る壮大な都市伝説の数々は、歴史の謎に魅せられた後世の人々によって創作された、壮大なアナクロニズム(時代錯誤)である可能性が極めて高い、と言わざるを得ません。
まとめ:なぜ私たちは「かごめかごめ」に惹きつけられるのか
この記事では、「かごめかごめ」という短いわらべうたを巡る、長い旅をしてきました。子供の頃に感じた漠然とした恐怖の正体から、徳川埋蔵金や明智光秀といった壮大な歴史ロマンを秘めた都市伝説、そして文献資料が示す歴史的な真実まで、その多層的な顔を一つひとつ見てきました。
最後に、これまでの内容を振り返りましょう。
- 「かごめかごめ」が怖い歌だと言われる最大の理由は、作者不詳で歌詞が曖昧であるために生まれた「意味の空白」に、人々が様々な恐ろしい物語を投影してきたためです。
- 徳川埋蔵金説や明智光秀説は、歴史のミステリーと歌を結びつけた、非常に魅力的で完成度の高い物語です。しかし、その根拠とされる歌詞の ключевые фразыは、彼らの時代よりもずっと後世に定着したものであり、史実の暗号と考えるのは困難です。
- 歴史的な資料を遡れば、「かごめかごめ」は江戸時代から伝わる、子供たちのための純粋で健全な遊び歌であったことが明らかです。
では、なぜ私たちは、その正体が子供の遊び歌であると知りながらも、なお「かごめかごめ」のミステリアスな魅力に惹きつけられてしまうのでしょうか。
結局のところ、「かごめかごめ」という歌は、**私たちの想像力を映し出す「鏡」**のような存在なのかもしれません。歌そのものに固定された一つの意味があるのではなく、私たちがその歌に何を見出そうとするか、どのような物語を読み取ろうとするかにこそ、本当の意味があるのです。
同じ歌が、ある人にとっては子供時代の楽しい遊びの記憶を呼び覚まし、ある人にとっては背筋も凍るような恐怖の物語を想起させ、またある人にとっては日本史の謎を解き明かす鍵となります。この驚くべき多様性こそが、「かごめかごめ」という文化が持つ、計り知れない豊かさの証明と言えるでしょう。
この記事を読み終えたあなたが、次に「かごめかごめ」のメロディを耳にしたとき、そこにどのような物語を思い浮かべるでしょうか。その答えは、もはや他の誰でもない、あなた自身の心の中にだけ存在しているのです。
↓こちらも合わせて確認してみてください↓
↓YouTubeで動画公開中♪↓
↓TikTokも更新中♪↓
↓お得商品はこちらから♪↓